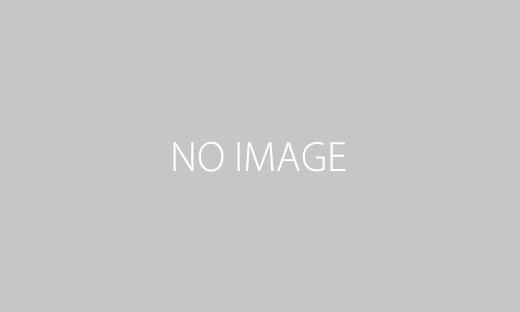NBL-エーテル共鳴について〜その2
1956年、イギリスの発生生物学者
コンラッド・ワディントン(Conrad Waddington)は
『Evolution』誌に論文を発表し、ミバエの実験において
環境刺激に反応して集団で獲得した特性が遺伝することを実証しました。
動物にとって好都合であれば、環境によって生じたいかなる変化も、
比較的短時間で遺伝的に同化される可能性があると指摘しています(The genetic assimilation of the bithorax phenotype. EVOLUTION 10: 1-13. March 1956.)。
ミバエの胚が、環境温度を変えたり、化学的刺激を与えたりするだけで、
胸部や翅の構造を変えるようになり、それが後世に伝えられます。
その子孫は、同じ環境刺激がないにも関わらず、
変化した構造を維持するようになります。
彼は、新しい特性を示す動物を選び、繁殖させました。
同じ環境刺激にさらすと、新しい特性を示す成体の割合が
さらに高い子孫が生まれました。
比較的少ない世代数の後、彼はその動物から繁殖させれば、
環境刺激を与えなくても新しい特性を
しっかりと受け継ぐことができることを発見したのです。
そして、この生物の形を変える影響を持つ環境刺激は、
「形態形成場(morphogenic field)」と呼ばれるようになります(Morphogenetic fields in embryogenesis regeneration and cancer: Non-local control of complex patterning. Biosystems. 2012 Apr 20109(3):243–261.)。
この発見は、ラマルクが観察したとされる
「獲得形質の遺伝」という環境による刺激による変態が
後世に受け継がれるという概念を実験的に証明したものでした。
この発見から、現代医学では、遺伝子の変化によらない遺伝、
つまり「エピジェネティックス(ワディントンが最初に使用した言葉)」
という分野が盛んになりました。
しかし、非常に残念なことはワディントンは
この現象を遺伝子ベースで考えていたため、
それ以上の拡がりを持たなかったことです
(遺伝子は、ウイルスと同じく厳密に実在することはまだ証明されていません)。
▼ここから先の記事の閲覧権限があるのは、
有料会員(個人会員、法人会員)の方でご購入者のみです。
※無料一般会員はご購入できません。
ニュースレターのバックナンバー記事を閲覧されたい有料会員の方は、下記からログイン後、ご購入してください。ご購入後、こちらのページに続きの文が表示されます。
1記事あたりの販売価格は、6SGD(シンガポールドル)です。